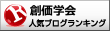中学生頃に哲学書に凝っていた時期がありました。皆さんも経験あると思いますが思春期の頃は「自分探し」をする時期がありますよね。私の「自分探し」は哲学書を読むことで十数冊の哲学書を読みました。その中で一番最初に学校の図書館で手にしたのが『ソクラテスの弁明』です。ソクラテス自身の著書はありません。『ソクラテスの弁明』は弟子のプラトンが書いたソクラテスの裁判記録です。ソクラテスは裁判にかけられ死刑宣告を受け毒杯を飲んで死にました。そんなソクラテスというと多くの人は【無知の知】という言葉を思い浮かべるのではないでしょうか。【無知の知】とは「自分には知識がないことを知る」という意味ですが、「自分に知識がない事を知っているのが智者である」と勘違いして理解している人を時折見かけます。この言葉はそういう意味ではなく「不知の自覚と知の追求」なんですね。自分の不知を知っているだけでは智者でもなんでもありません。創価学会員のように「知らない事すら知らない」「知らない事を知ったかぶり」する人間よりも賢いですがそれでは不十分です。自分が知らないという事を自覚しその不知を追求することが大切なのです。「不知を追求し続ける」ことが「知」であり、真理の追求を続けること自体が哲学であるとソクラテスは示しています。これは信仰も同じで「死」という不知を追求しそこからより良い人生を追求するのが宗教です。御利益あるとか罰が当たるとかそういうモノは表層上のモノで宗教の本質ではありません。哲学との違いは哲学は「疑」によって宗教は「信」によって不知を追求することです。また哲学と宗教の大きな相違点は、哲学は思考のみで行動が伴いませんが宗教は行動が伴います。私が哲学書を読むのを止めたのは哲学にはその理想を実現する具体的且つ普遍的な行動が示されていなかったからです。人は必ず死にます。その絶対的な死に対し人は不知なのです。その不知を自覚して死に対する思索するのが信仰(宗教)です。ですから無信論は「不知の追求」を放棄した姿であり、ただの【無知の知】です。死が不知であることは誰でも知っています。宗教とは死と向き合うことによって自分の人生をより豊かに幸福に生きる術なのです。
▼一日「イチ押し」お願いします