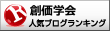X(ツイター)で仏教学者兼浄土宗僧侶の清水俊史氏とほんの短いやり取りをした。実は私は彼の著書の『ブッタという男』を読んでいるので彼に多少の興味があったから、彼が御義口伝を偽書と断定しているポストを読み御義口伝が偽書ならば「いつ・どこで・誰が御義口伝を書いたのか?」質問をしたところ「いつ誰がどこで書いたかは重要ではない」という全く質問をスルーした回答をもらった。この質問の答えは「いつ誰がどこで書いたか」を具体的答えるか或いは「知らない」の二択である。ところが「重要じゃない」とか「一般的には偽書とされている」などと質問に答えない詭弁的回答で正直残念に思った。自宗派の文書を偽書というのは自由だが他宗派の文書を偽書と発言するのであれば確固たる証拠を示すべきだろう。それが出来ないなら安直な発言をしないか、自分が無知であることを素直に認めればいいだけの話なのだが彼のプライドがそれを許さなかったのだろうか(なんとなく犀角独歩氏に似ている)。しかも最後にはほぼ捨て台詞を吐いているところがちょっと情けない。仏教学者だか僧侶だかベストセラー作家だか知らないが、不都合な質問に対し誤魔化して押し切ろうとして最後は捨て台詞では創価学会員と変らなくだろう。またXのやりとりでは「正宗にしか伝わっていなくて正宗に都合のいい文書で表に出せる写本もない」から御義口伝や他の相伝書を偽書だと主張しているが、これらは偽書を証明する証拠にならない。「それは貴方の感想ですよね?」の世界だ。そもそも正宗の相伝書なのだから正宗にしか伝わっていないのは当然だし、正宗に都合がいい文書なのではなくその相伝によって法門・宗義を立てているのが正宗だし、相伝書の写本を表に出す必要など全くない。所詮、偽書と主張する人達は写本を提示してもその主張を変えることはないのだからそんな狂人走れば不狂人も走るようなマネをする必要はない。清水氏は宗教に素人というわけではなく僧侶という宗教家の肩書があるのに相伝書の意味や意義も分からないのかと少し驚いた。また仏教学者ならば個人的感想ではなくもう少しアカデミックな回答が欲しかった。そこら辺の創価学会員と変わらないような回答で宗教家としても学者としても中途半端感を感じた。対論慣れしていないのだろうけど僧侶とか学者とかそんな権威的詭弁が全ての相手に通用すると思っているのだろうか。さて折角だから清水氏の著作『ブッタという男』のレビューも書くと、分かる人もいるだろうがこの本のタイトルは田川建三氏の書著『イエスという男』のパクリで内容も田川氏のイエス論をブッタ論に置き替えたような内容。田川氏も今までのキリスト教の歴史や解釈を変更し多くの神学学者や歴史神学者をディスっているが清水氏の論調は田川氏の著作の二番煎じ感が拭えない。個人的な新たな仮説を立てることは全然悪い事は思わないが、彼の主張に対するエビデンスは偏っているように思えるし理論構成も自己矛盾している部分が多い。思うに清水氏の仮説は「結論ありき」の確証バイアスがかかっているのだろう。また彼の主張は中村元氏等の説を否定し凌ぐほどの説得力など皆無だ。中村元氏と彼と比べるのは中村元氏に失礼だろう。彼の個人的見解を断言してしまうと強引や傲慢さを与えてしまう。そんなわけで『ブッタだという男』という書籍は推理小説感覚で読む分には面白いかも知れないが、仏教を真面目に知りたい・興味があるという方にはおススメはできない。前述の御義口伝に関する短いやりとり同様にこの書籍も全般的に牽強付会の説に充ちている。そんなわけでこの書籍は仏教をある程度学んだ後に読んで、納得できる部分とそうではない部分を分別できるくらいの知識・知見がないと初手から仏教を誤解してしまう。またこの書籍だけではなく中村元氏らの著書も読み比較検討も必要だ。それはともかくとして『ブッタという男』の筆者である【清水俊史という男】とXの短いやり取りができたことはいつか彼の書籍の書評を書こうと思っていた私にとってはいいキッカケができたので収穫だった。そこでもう一度『ブッタという男』を読み返そうとも思ったが、私は清水説より中村説を支持しているし他にも読みたい本があるのでまだしばらくは本棚に眠らせておくことにした。
▼一日「イチ押し」お願いします!